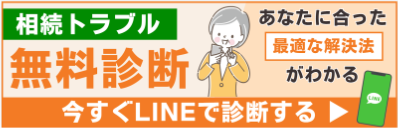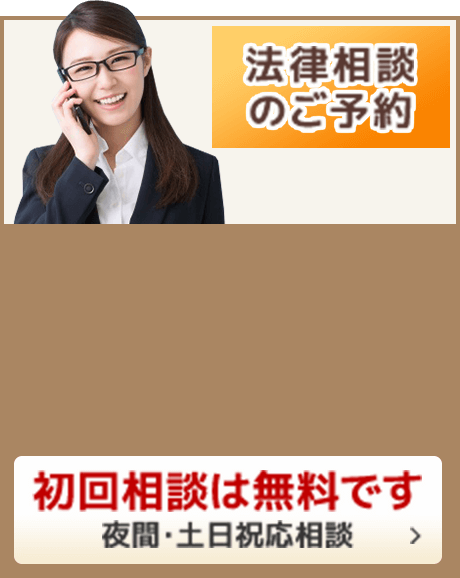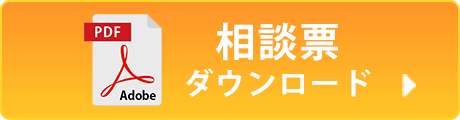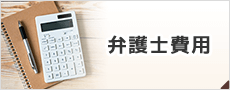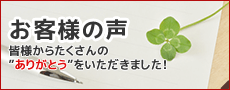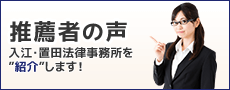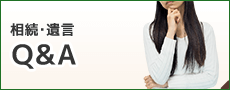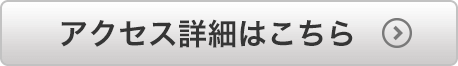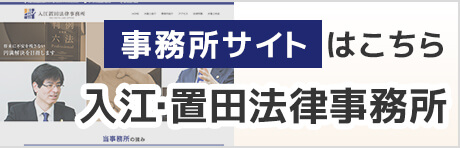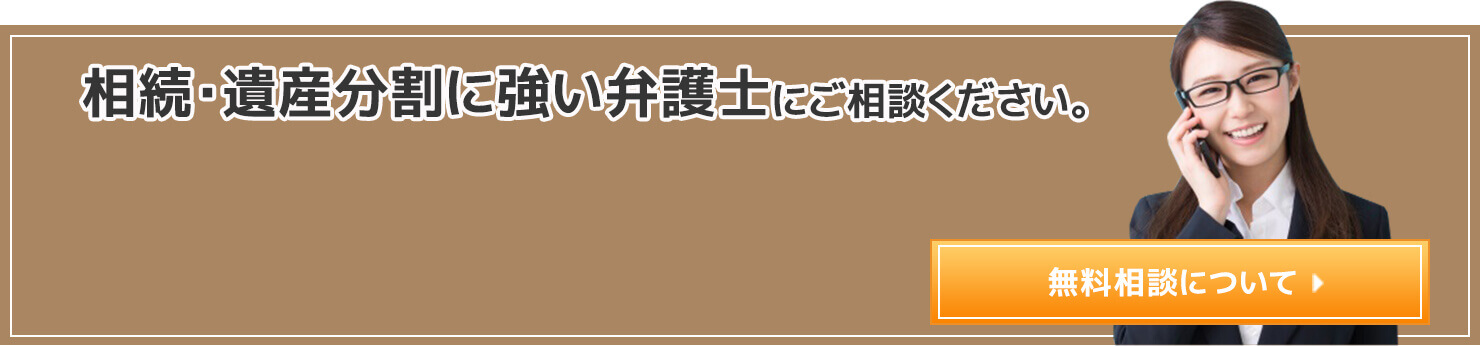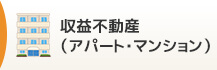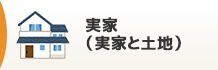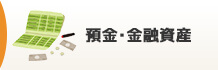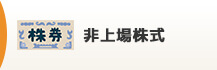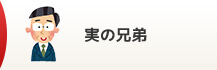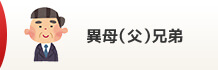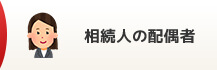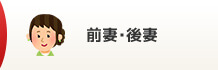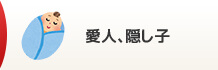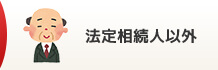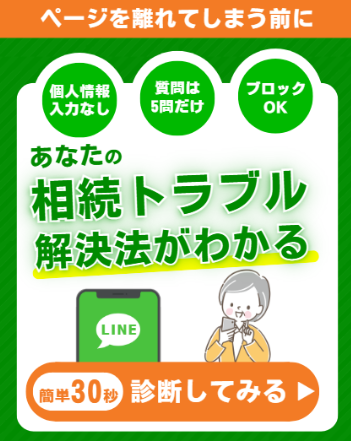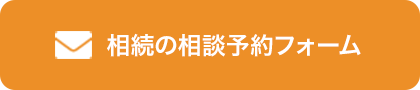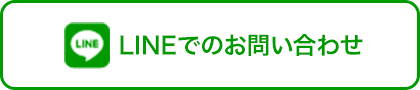生前贈与のQ&A
Q1)生前贈与とは何ですか?
A1) 人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく生きているうちに贈与で財産をもらうことです。
Q2)生前贈与をすると、何かメリットがあるのですか?
A2) 生きているうちに財産をもらえるため、相続のときに争いになりません。相続の争いは莫大な費用がかかりますが、それを回避する事ができます。
Q3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?
A3) 贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。また, 相続税が高額になるような方の場合は,生前贈与を活用したほうが,たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので,贈与税は全て高いという思い込みは 一度忘れて検討することも必要です。
Q4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?
A4) 相続時精算課税制度と、夫婦間贈与の特例というものがあります。
Q5)相続時精算課税とは何ですか?
A5) 贈与した年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母など(「特定贈与者」と言います)から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子又は孫などへ贈与する場合に選択できる贈与税の制度のことを、相続時精算課税といいます。
相続時精算課税が適用されると、贈与を受けた者に課される贈与税の額は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(「課税価格」と言います)から、相続税時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、限度額を2500万円とする特別控除額を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて計算されます。
ただし、相続時には相続財産として再度評価し精算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると従来の歴年課税には戻れませんので、専門家に相談することをおすすめします。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を控除した後の金額に贈与税の税率を適用して贈与税額を計算します。
Q6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか?
A6) 子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでしたが、平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用できるようになりました。
Q7)税務申告は、どのように行うのですか?
A7) この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、必要書類をつけた「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
Q8)贈与税以外にかかる経費はありますか?
A8) 不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払います。
Q9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか?
A9) 毎年4~5月頃、その不動産の所在地を管轄する市町村からご自宅に郵送される固定資産税納付通知書に記載されています。また市区町村役場の税務課等で評価額証明書を発行してもらえます。
Q10)不動産の名義はどうやって変えるのですか?
A10) 不動産の名義を変える申請書に必要書類をつけて法務局に提出します。専門知識が必要なため、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
- 相続税申告はお任せください!
- 相続税がかかるか心配な方へ
- 相続税の仕組みと申告
- 相続税評価額の算出
- 家族信託(民事信託)を活用した複雑な相続の生前対策
- 遺言のQ&A
- 上手な贈与の利用方法
- 相続手続き丸ごとサポート
- 海外に在住している相続人がいる場合
- 申告書を自分で作成したい方へ!相続税に関する無料相談実施中!
- 生前贈与のQ&A
- 【弁護士×税理士コラム】弁護士・税理士の違いとダブルホルダーに依頼するメリットを徹底解説
- 【弁護士×税理士コラム】遺留分トラブルを回避し、相続税を「実質ゼロ」にする戦略
- 【弁護士×税理士コラム】相続税の申告期限が迫る方へ。「未分割」で放置すると数千万円の損をする理由
- 相続税計算シミュレーション
- 相続税の基礎控除とは?専門家が徹底解説!
- 相続税の計算方法を徹底解説!
- 税務署からの相続税についてのお知らせが届いた方へ
- 相続税・相続税申告のQ&A
- 相続税の期限後申告とは?専門税理士が解説!
- 相続税申告サポート
- 相続税の無料相談
こんなお悩みありませんか?
相続相談解決事例
相続の争点
この記事の執筆者

入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)