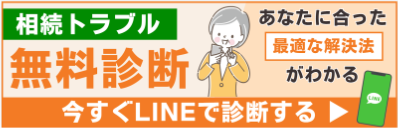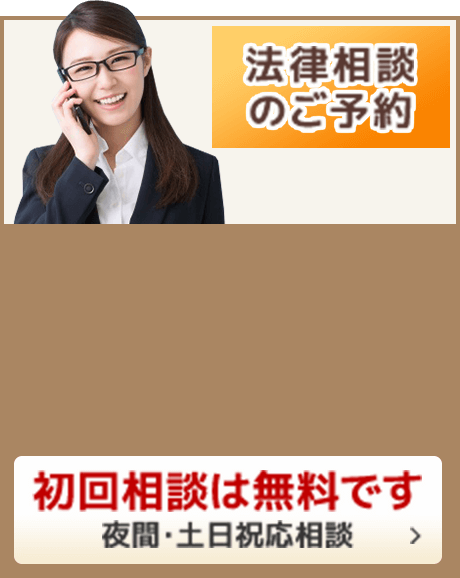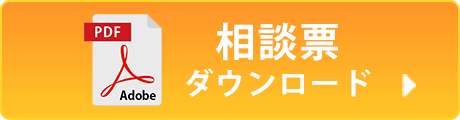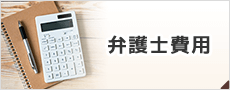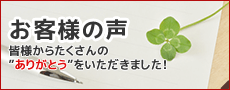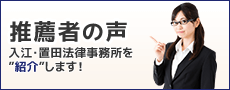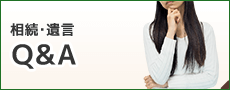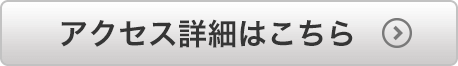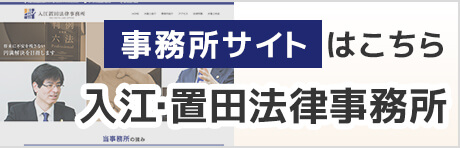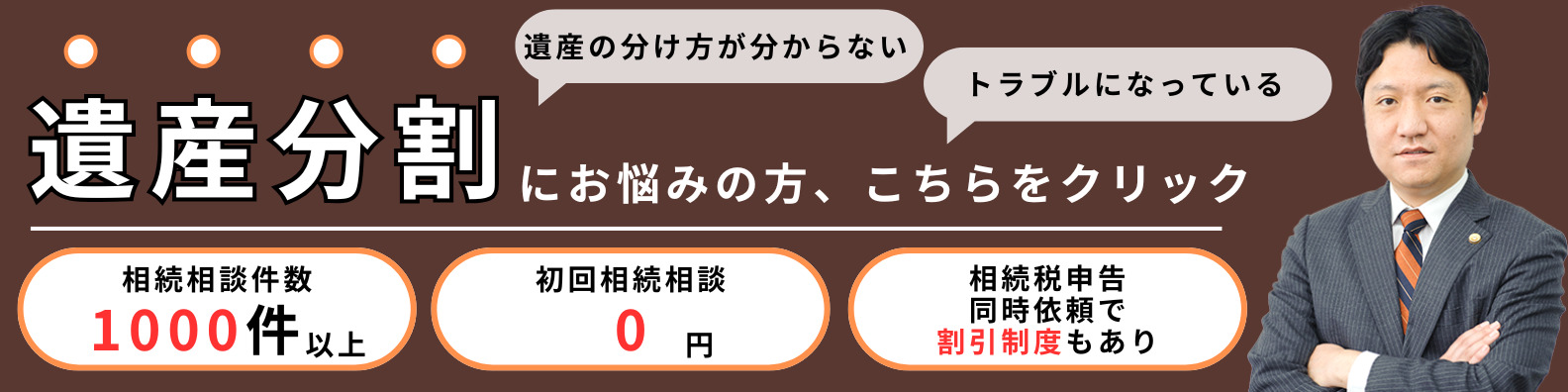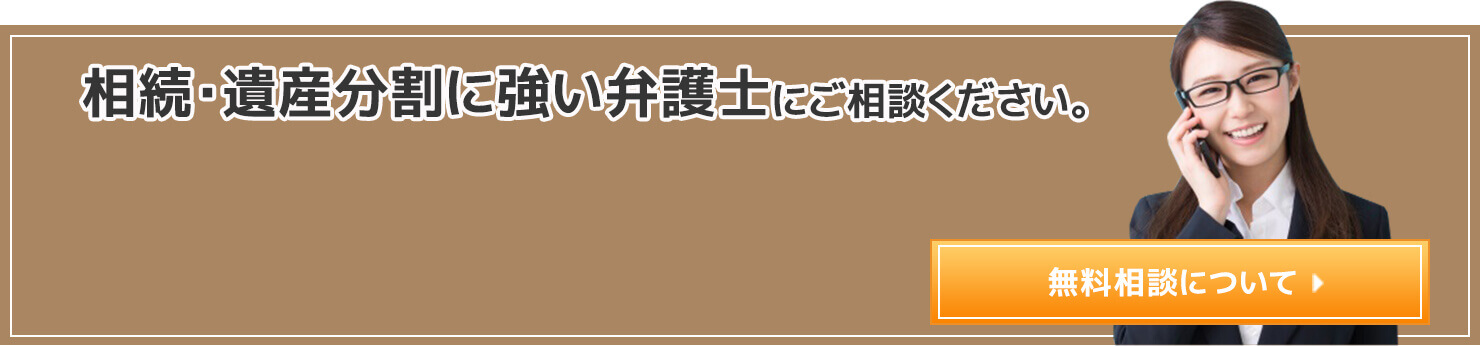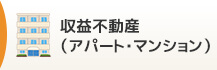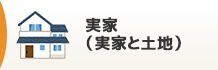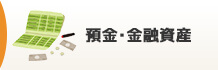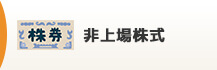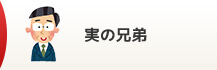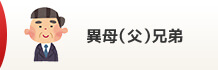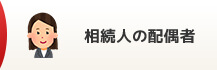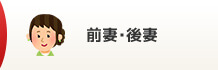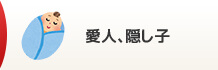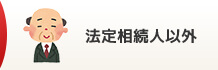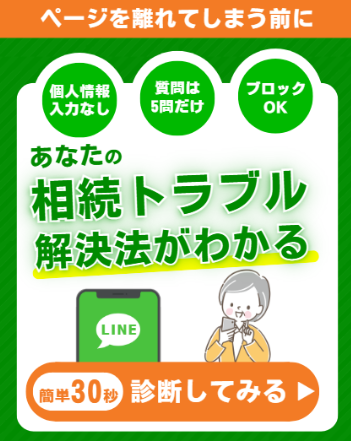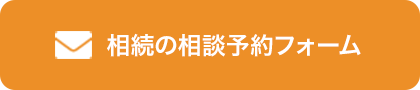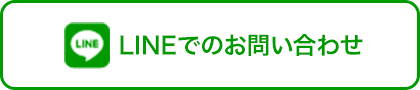行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
弁護士の置田です。
遺産分割の手続きを進めようとした際に、相続人の一人が行方不明だったり、連絡が取れなくなってしまうと、どう進めたら良いか分からず困っている方も多いでしょう。法律上、遺産分割には全相続人の同意が必要ですが、一人でも音信不通だと手続きが大きく滞ります。
この記事では、行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割の対応手順について解説します。さらに、弁護士に依頼するメリットや、実際の解決事例も紹介します。
このコラムを読むことで、複雑なケースにおける遺産分割の進め方が理解でき、具体的な初期対応のポイントが分かります。特に、「行方不明の相続人がいて手続きが進まない」「どうやって弁護士に相談するべきか知りたい」という方に読んでいただきたい内容です。
行方不明や音信不通の相続人がいる場合の問題点
相続において音信不通の相続人がいると、遺産分割協議が進行しないため、様々な問題が発生します。
-
法的に全員の同意が必要
- 遺産分割協議では、すべての法定相続人が合意する必要があります。一人でも行方不明の場合、協議自体が成立しません。
-
相続税の申告遅れによるペナルティ
- 相続税の申告期限は死亡から10ヶ月以内ですが、音信不通の相続人がいる場合、この期限を守ることが難しくなり、延滞税や加算税のリスクが発生します。
-
他の相続人への負担
- 長期間の手続き停滞により、他の相続人の精神的・経済的な負担が大きくなります。
行方不明や音信不通の相続人がいる場合の対応方法
1.戸籍の附票の取り寄せ
行方不明や音信不通の相続人の戸籍の附票を取り寄せれば、その者の現在の住民票上の住所地が判明します。その住所地宛に手紙を送付するなどによって連絡を試みます。また、実際にその住所地を訪れて、その相続人が居住しているかどうかについて現地調査を行ったりもします。
それでも、その相続人がそこに居住していなかったり、依然として行方不明のままであったりした場合は、次の「不在者財産管理人の選任申立て」又は「失踪宣告の申立て」を検討します。
2. 家庭裁判所への「不在者財産管理人」の選任申立て
家庭裁判所に「不在者財産管理人」を申立て、不在者に代わり管理人が遺産分割協議に参加します。管理人の選任が認められると、協議が円滑に進められるようになります。
-
申立てに必要な書類
戸籍謄本や不在者の住民票除票、申立書などを準備します。
-
管理人の役割
- 不在者の財産を適切に保全し、その利益を守りながら協議に参加します。
3. 失踪宣告の申立て
7年以上音信不通の相続人に対しては、家庭裁判所に失踪宣告を申立て、法的に死亡したと見なすことが可能です。これにより、遺産分割の手続きを進めることができます。
-
申立ての手順
- 家庭裁判所に申立てを行い、公告期間を経て失踪宣告が認められます。
-
注意点
- 失踪宣告後に本人が戻った場合、再び遺産分割協議を行う必要が生じる可能性があります。
相続人が戸籍の附票上の住所地に居住しているであろうにもかかわらず、一向に連絡がつながらない場合の対応方法
連絡がとれない相続人を相手に家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てます。連絡がとれない相続人に不利益がない内容であれば、遺産分割調停における調停に代わる審判又は調停から審判へ移行した上での遺産分割審判を受けることができます。
弁護士に依頼するメリットと必要性
弁護士に依頼することで、遺産分割に関する煩雑な手続きや書類作成を代行し、迅速な解決を目指せます。
-
法的手続きの代行
家庭裁判所への申立てや公示催告などの複雑な手続きを弁護士が代行します。
-
相続人間の調整
- 感情的な対立がある場合も、中立的な立場から適切な調整が可能です。
-
早期解決が可能
- 迅速な初期対応により、長期化するリスクを回避します。
弁護士が提供する初期対応サポート
弁護士は、行方不明の相続人がいるケースでも、初期対応を的確に行います。
-
相続人の確認
相続人全員の戸籍を調査し、法定相続人を確定します。
-
必要書類の作成
申立てに必要な書類を準備し、家庭裁判所への提出をサポートします。
-
相談者へのアドバイス
今後の手続きに関する見通しや、必要な対応策を提案します。
具体的な遺産分割事例と初期対応方法
ケーススタディ:音信不通の兄がいる場合の遺産分割
依頼者Aの事例では、父親の遺産を分割する際に、長男が10年間音信不通となっていました。
-
初期対応
公示催告を行い、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任しました。
-
結果
管理人の調整で遺産分割協議が成立し、無事に手続きを完了しました。
弁護士に遺産分割について相談する重要性
行方不明や音信不通の相続人がいる場合、弁護士に相談することで迅速かつ確実な解決が期待できます。特に、家庭裁判所への申立てや書類作成のサポートは専門家の力が必要です。
-
-
まとめ
行方不明や音信不通の相続人がいる場合、遺産分割協議が停滞し、他の相続人にも負担がかかります。この記事では、家庭裁判所への申立てや失踪宣告の手順、弁護士のサポートを活用した解決方法を紹介しました。
複雑な相続手続きでお困りの方は、ぜひ弁護士に相談してください。初回の無料相談で状況を共有することで、最適な解決策が見つかるはずです。
- 行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
- 認知症の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
- 未成年の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
- 婚外子の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
- 面識のない相続人がいる場合の遺産分割について弁護士が解説!
- 相続人が多数いる場合の遺産分割について弁護士が解説!
- 遺産分割問題解決の流れ
- 収益不動産を相続したい方へ
- 相続調査について
- 遺産分割協議と遺産分割協議書
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割訴訟について
- 円満な遺産分割を終えることを望まれる方へ
- すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方
- ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ
- 不動産の相続を避け、故人の他の相続財産を相続したい方へ
- 遺産分割を放置しておくと大変なことに!
こんなお悩みありませんか?
相続相談解決事例
相続の争点
この記事の執筆者

入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)