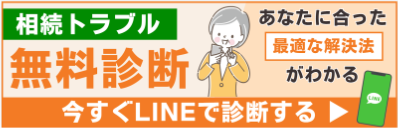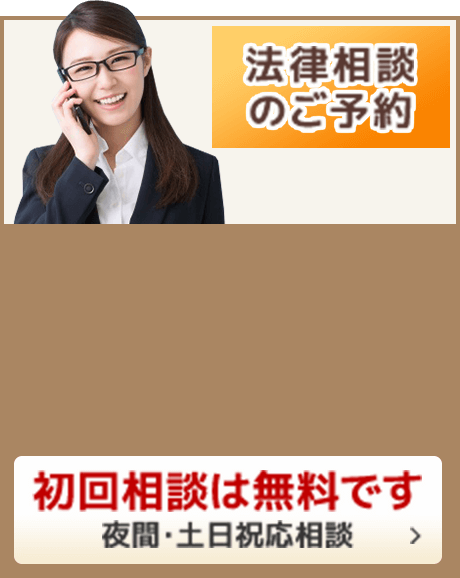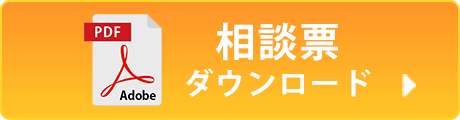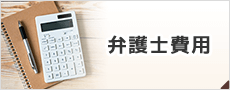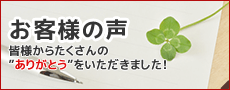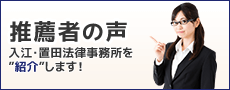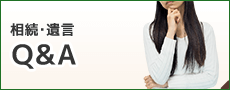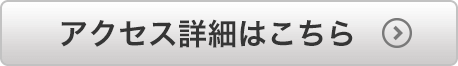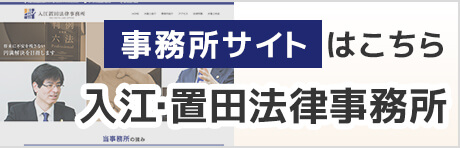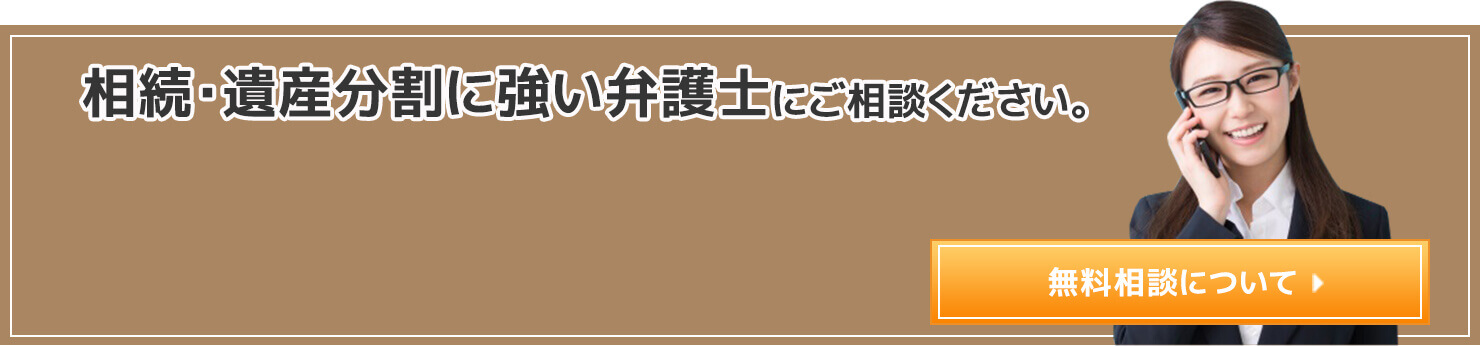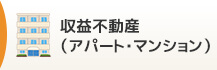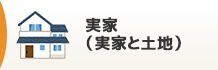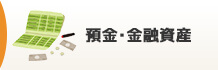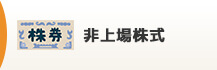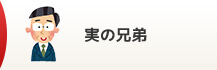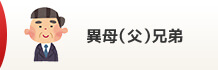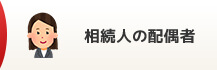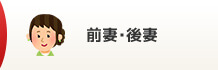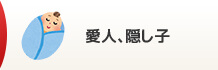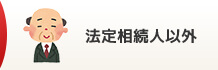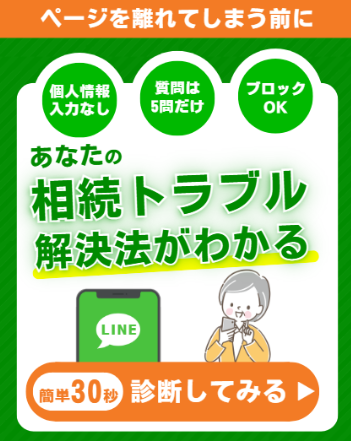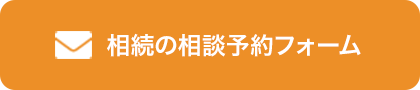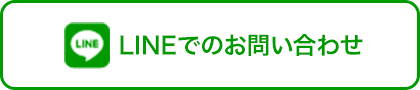認知症の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
認知症の相続人がいる場合の遺産分割について弁護士が解説
「親が認知症と診断されたけど、遺産分割はどうなるの?」「成年後見制度って聞いたことはあるけど、実際にはどんな手続きが必要なの?」
認知症の家族がいる場合、相続について様々な不安や疑問を抱える方が多いのではないでしょうか。認知症の方は、判断能力が低下しているため、遺産分割協議に参加することが難しい場合があります。そのため、遺産分割の手続きが複雑化したり、思わぬトラブルに発展したりする可能性も考えられます。
この記事では、認知症の相続人がいる場合の遺産分割について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。成年後見制度や遺産分割協議の手順、注意点などを詳しく説明することで、読者の皆様が抱える疑問や不安を解消し、スムーズな遺産分割を実現できるようサポートいたします。
この記事を読むことで、以下の点が理解できます。
- 認知症の相続人がいる場合の遺産分割の基礎知識
- 成年後見制度の役割と手続き
- 遺産分割協議をスムーズに進めるための方法
- トラブルを回避するための注意点
- 弁護士に依頼するメリット
この記事は、認知症の家族がいる方や、将来に備えて認知症と相続について知っておきたい方に向けて書いています。ぜひ最後まで読んで、遺産分割に関する知識を深めてください。
遺産分割とは?
遺産分割とは、亡くなった方の遺産を、相続人で分割することをいいます。遺産には、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
民法では、遺産分割について以下のように定めています。
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(民法第898条)
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。(民法第906条)
つまり、相続が発生すると、相続人は自動的に遺産を共有することになり、その共有状態を解消するために遺産分割協議を行う必要があるのです。
遺産分割協議の方法
遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決めることです。遺産分割協議が成立するためには、すべての相続人の同意が必要です。
遺産分割協議では、以下のような事項を決定します。
- 各相続人が取得する遺産
- 遺産に負債がある場合の処理方法
- 相続財産の評価方法
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、遺産分割の内容を明確にし、後々のトラブルを防止するために重要な書類です。
遺産分割協議が成立しない場合
相続人全員の同意が得られず、遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意が成立しない場合は、家庭裁判所が審判によって遺産分割の方法を決定します。
弁護士としての見解
遺産分割は、相続人間で感情的な対立が生じやすく、トラブルに発展しやすいものです。特に、相続人の人数が多い場合や、遺産に不動産が含まれている場合は、複雑な手続きが必要となることがあります。
遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続人間で十分なコミュニケーションを図り、お互いの意見を尊重することが大切です。また、必要に応じて、弁護士などの専門家に相談することも有効です。
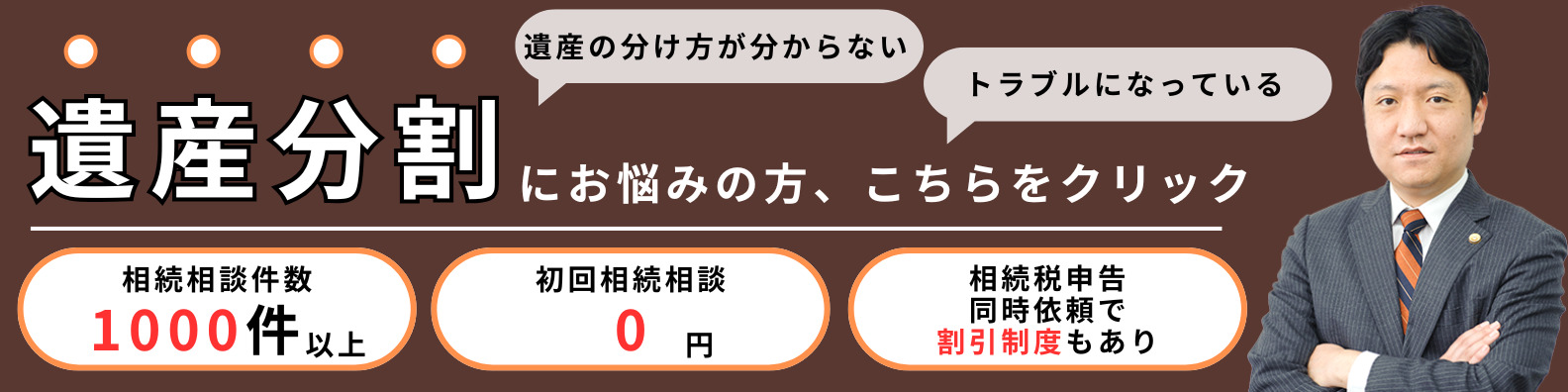
認知症の相続人がいる場合の問題点
認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議を進める上で、いくつかの問題点が生じます。
判断能力の欠如
認知症の方は、病状の進行によって判断能力が低下しているため、遺産分割協議の内容を理解したり、自分の意思を表明したりすることが難しい場合があります。
そのため、認知症の方が遺産分割協議に参加する場合、その方が本当に理解した上で同意しているのか、判断能力が十分にあるのかという点が問題となります。
意思表示の困難さ
認知症の方は、自分の意思を明確に伝えることが難しい場合があります。そのため、遺産分割協議において、本人の真意が反映されないまま手続きが進んでしまう可能性があります。
不当な影響を受けやすい
認知症の方は、周囲からの影響を受けやすく、判断能力が低下していることを利用して、不当な遺産分割を迫られる可能性があります。
弁護士としての見解
認知症の相続人がいる場合、本人の権利を守るために、適切な対応が必要となります。
具体的には、成年後見制度を利用することで、本人に代わって遺産分割協議に参加したり、財産を管理したりすることができます。また、弁護士に相談することで、不当な遺産分割を防止し、本人の意思を尊重した遺産分割を実現することができます。
認知症の相続人がいる場合の対応手順
認知症の相続人がいる場合、遺産分割の手続きは、以下の手順で行います。
-
成年後見制度の利用
- 認知症の相続人がいる場合は、家庭裁判所に成年後見開始の審判を申し立て、成年後見人を選任します。
-
遺産分割協議
- 成年後見人が、他の相続人と遺産分割協議を行います。
-
遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
-
遺産の名義変更
- 遺産分割協議書に基づき、遺産の名義変更手続きを行います。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方を保護するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産管理や法律行為を行います。
成年後見制度には、以下の3つの種類があります。
-
後見
- 判断能力が著しく低下している場合に利用されます。
-
保佐
- 判断能力が不十分な場合に利用されます。
-
補助
判断能力がやや不十分な場合に利用されます。
認知症の程度に応じて、適切な制度を利用する必要があります。
成年後見人の役割
成年後見人は、本人の利益を最優先に考えて、以下の役割を担います。
-
財産管理
- 預貯金の管理、不動産の売却など、本人の財産を管理します。
-
法律行為
- 遺産分割協議、契約の締結など、本人に代わって法律行為を行います。
-
身上監護
- 本人の生活を支援し、介護サービスの利用などを手配します。
弁護士としての見解
成年後見制度を利用することで、認知症の相続人の権利を守り、適切な遺産分割を行うことができます。ただし、成年後見制度の手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合もあるため、弁護士に相談することをお勧めします。
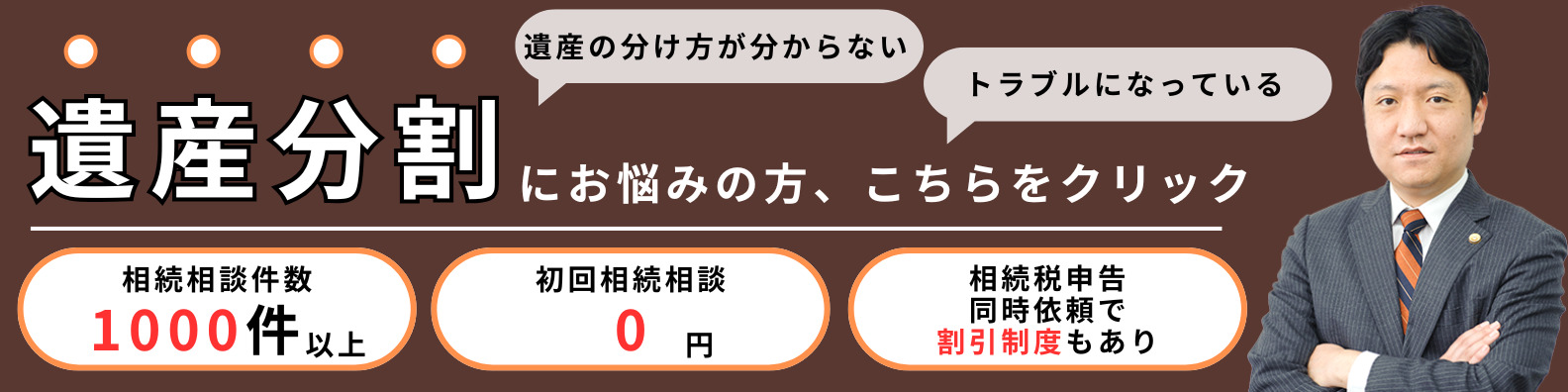
弁護士に依頼するメリットと必要性
認知症の相続人がいる場合の遺産分割では、弁護士に依頼するメリットが大きいです。
専門的な知識と経験
弁護士は、相続に関する専門的な知識と豊富な経験を持っています。そのため、複雑な法律問題や手続きにも対応することができます。
客観的な立場からのアドバイス
弁護士は、感情的な対立に巻き込まれることなく、客観的な立場からアドバイスを提供することができます。
トラブルの予防と解決
弁護士に依頼することで、遺産分割協議をスムーズに進めることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。また、トラブルが発生した場合でも、弁護士が交渉や調停、訴訟など、適切な対応を行います。
手続きの負担軽減
弁護士に依頼することで、成年後見制度の利用や遺産分割協議、名義変更などの手続きを任せることができます。
弁護士としての見解
認知症の相続人がいる場合の遺産分割は、法律的な問題や手続きが複雑になりがちです。弁護士に依頼することで、手続きの負担を軽減し、安心して遺産分割を進めることができます。
特に、以下のような場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
- 相続人が多い
- 遺産に不動産が含まれている
- 相続人間で意見が対立している
具体的な遺産分割事例と初期対応方法
ケーススタディ1:認知症の親と、その子供2人のケース
被相続人が母親で、相続人が父親と子供2人のとき、父親が認知症を患っているというケース、です。
初期対応方法
- 父親の認知症の程度を確認し、成年後見制度の利用を検討します。
- 遺産の状況を把握します。預貯金、不動産、借金など、どのような遺産があるのかを調べます。
- 子供2人で話し合い、遺産分割の方針を決定します。
- 弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成や成年後見手続きなどを依頼します。
ケーススタディ2:認知症の兄弟姉妹がいるケース
被相続人が兄弟姉妹の一人で配偶者も子もおらず、、他の兄弟姉妹が相続人となるところ、そのうち一人が認知症を患っているというケースです。
初期対応方法
- 認知症の兄弟姉妹の状況を確認し、成年後見制度の利用を検討します。
- 遺産の状況を把握します。預貯金、不動産、借金など、どのような遺産があるのかを調べます。
- 兄弟姉妹で話し合い、遺産分割の方針を決定します。
- 弁護士に相談し、遺産分割協議書の作成や成年後見手続きなどを依頼します。
弁護士としての見解
認知症の相続人がいる場合の遺産分割は、それぞれのケースによって対応方法が異なります。上記のようなケーススタディを参考に、ご自身の状況に合わせて適切な対応を行うようにしましょう。
初期対応を誤ると、後々になって大きなトラブルに発展する可能性もあります。そのため、早めに弁護士に相談し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
まとめ
この記事では、認知症の相続人がいる場合の遺産分割について解説しました。
認知症の相続人がいる場合、遺産分割の手続きは複雑化し、トラブルに発展する可能性も高くなります。成年後見制度の利用や弁護士への相談など、適切な対応を行うことで、スムーズな遺産分割を実現することができます。
遺産分割でお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、親身になってサポートいたします。
認知症の相続人がいる場合の遺産分割でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
初回相談は無料です。
電話での相談予約は、06-6556-6613にお電話ください
- 行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
- 認知症の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
- 未成年の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
- 婚外子の相続人がいる場合の遺産分割とは?弁護士が解説!
- 面識のない相続人がいる場合の遺産分割について弁護士が解説!
- 相続人が多数いる場合の遺産分割について弁護士が解説!
- 遺産分割問題解決の流れ
- 収益不動産を相続したい方へ
- 相続調査について
- 遺産分割協議と遺産分割協議書
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割訴訟について
- 円満な遺産分割を終えることを望まれる方へ
- すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方
- ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ
- 不動産の相続を避け、故人の他の相続財産を相続したい方へ
- 遺産分割を放置しておくと大変なことに!
こんなお悩みありませんか?
相続相談解決事例
相続の争点
この記事の執筆者

入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)