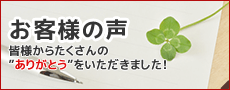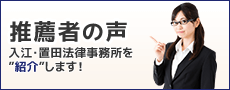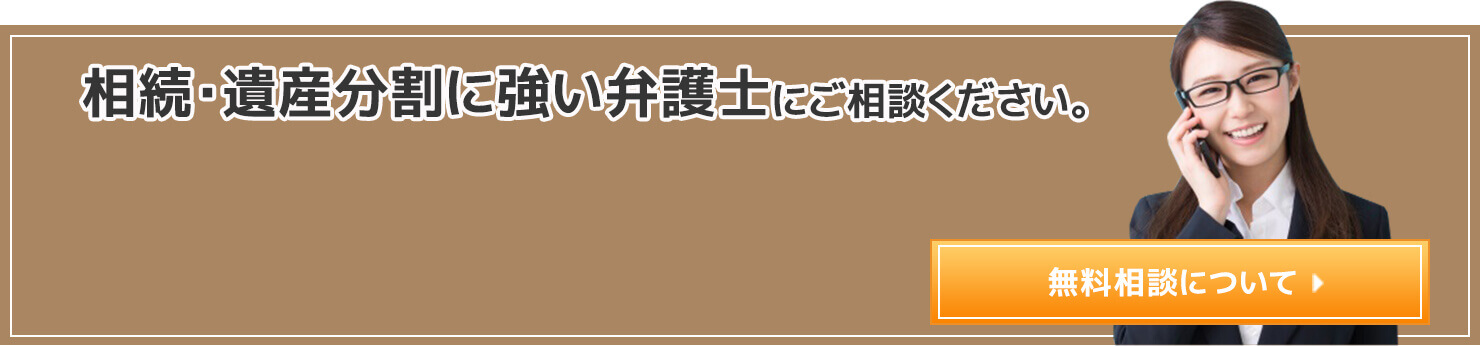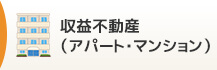解決事例
- 2023.01.27
- 被相続人のすべての遺産について死因贈与を受けたとして、遺産に関する紛争調停を申し立てられた事例
事案
亡くなられたお父様(被相続人)には長女と二女の2名の相続人がおられました。遺産としては、預貯金(現在残高約1600万円)と、被相続人が長女とともに居住していた不動産(固定資産税評価額約300万円)がありました。今回は、二女からご相談戴いた事例です(以下では、二女のことを「依頼者」と言います。)。
生前、被相続人が脳梗塞のため入院したことを機に、長女が被相続人の預金通帳を管理するようになりました。長女は、自ら飲食店を経営しており、コロナ禍の影響で店の経営も芳しくなかったことから、被相続人から了解を得て、被相続人の預金口座からお金を引き出し、店の経営資金に充てるなどしていたとのことでした。
その後、被相続人が亡くなった後に、長女から依頼者に対し、被相続人と自分との間ですべての遺産に関する死因贈与契約が成立していたので、本来は預貯金や自宅不動産は自分に相続する権利があるが、紛争を長引かせたくないので、亡くなった時点で残っている遺産を2分の1ずつ分割するのでどうかといった内容の提案がありました。依頼者としては、長女が被相続人から合計1800万円にも上る生前贈与(又は被相続人の了解を得ないでした預金の使い込み)を受けていたことが全く反映されていないことに納得ができず、長女からの提案を拒否しました。そうしたところ、長女から、遺産に関する紛争調停を申し立てられたのが本事案になります。
解決方針
依頼者は、長女から調停を申し立てられた段階でご相談に来られ、当事務所が依頼者の代理人として対応することとなりました。調停手続の中で、代理人の方から、長女が主張する死因贈与契約の成立について、客観的証拠を提出するよう求めたところ、長女が撮影したとされる被相続人の生前の様子を写した動画データが提出されました。ところが、その動画データは、被相続人が「〇〇(長女の名前)に全部あげます。□□(二女の名前)にはあげません。」とのセリフを述べている様子が、わずか10秒ほど撮影されたものに過ぎませんでした。
そこで、代理人において、このような動画データだけで、被相続人と長女との間に死因贈与契約が成立していたとは到底言えないと主張するとともに、死因贈与契約が成立していないことを前提に、長女が受けた生前贈与(合計1800万円)が特別受益に該当するため遺産に持ち戻すべきことを主張しました。
被相続人と長女との死因贈与契約が認められず、かつ、長女の特別受益が認められるとすると、長女はすでに遺産と同額程度の特別受益を受けていたことになり、遺産はすべて依頼者が取得するとの分割方法にもなり得るところでした。もっとも、自宅には長女が現に居住しており、引き続き自分が相続して住み続けたいとの長女側の意向がありましたので、そこは依頼者も妥協し、自宅は長女が、預貯金は依頼者が、それぞれ取得するとの分割方法を提案しました。
結果
その結果、裁判所も、こちらの調停案に理解を示して戴き、長女側を説得した上で、最終的には当方が提示した内容での遺産分割調停が成立するに至りました。
当事務所コメント
生前に被相続人から遺産をあげると言われていたとして、相続人から(又は相続人以外の第三者から)死因贈与契約が成立していたとの主張がなされることが、相続紛争の実務においてしばしばあります。この場合、死因贈与契約が有効に成立していたといえるのか否か、裁判所がどのような判断を下す可能性が高いのかを、専門家を交えてしっかりと検証する必要があります。
この点、契約書などの客観的資料が作成されていた場合には、死因贈与の成立が認められる可能性は相応にあると言えますが、実務上は、単に口頭で言われたに過ぎないなど、客観的証拠による裏付けを欠くことが多々あります。
本事例においても、長女から被相続人の様子を撮影した動画データが提出されましたが、単に「〇〇(長女の名前)に全部あげる」と言っているだけでは、贈与の対象がはっきりとしませんし、死因贈与なのか生前贈与なのかもはっきりしません。いつ撮影されたものであるのすらわかりません。このような証拠だけでは死因贈与契約の成立が認められることはまず困難だろうとの見通しの下、本調停に臨みました。
相手方が主張する内容が、法的な観点から審理に堪えうるものか、客観的な証拠に基づくものといえるのかどうかについては、専門家である弁護士こそ検証し得るものです。相手方の主張の当否を判断する上では、是非とも弁護士にご相談ください。
こんなお悩みありませんか?
相続相談解決事例
相続の争点
この記事の執筆者

入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)