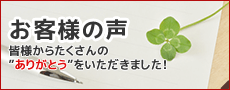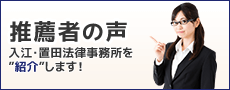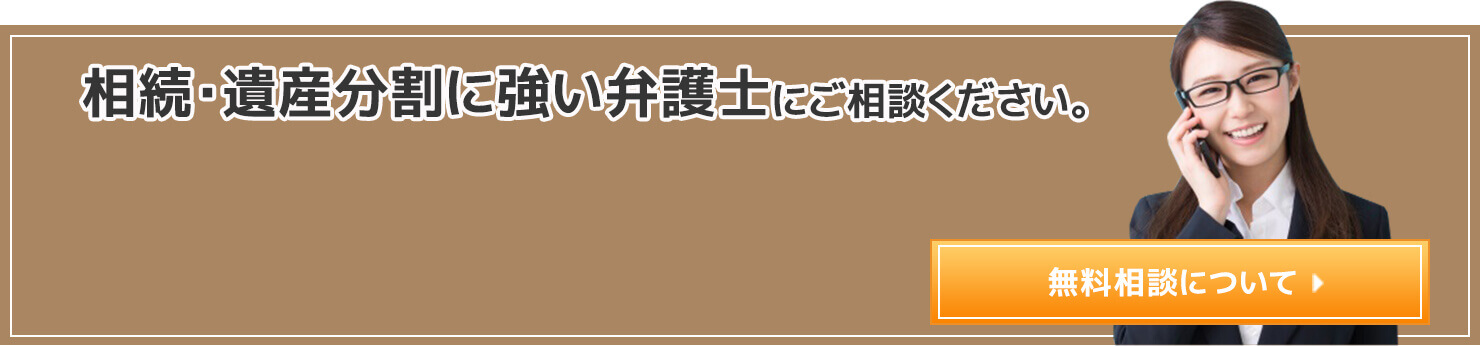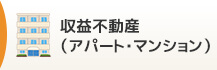解決事例
- 2020.09.04
- 遺産分割協議成立後に遺言書の存在が明らかとなり、遺産分割協議の錯誤無効を争った事例
事案
| 相談者の夫(被相続人)は、若くして事業に成功され、東京都内のとある高級住宅街に建つ立派な邸宅(時価約1億円)を購入され、夫婦で一緒に暮らしてきました。相談者と被相続人との間には3人の子ども(長男、二男、長女)がいましたが、3人とも実家を離れ、別所帯を持っていました。 長女の夫は,結婚当初、被相続人の事業の跡取りとして迎え入れられ、被相続人ら夫婦と養子縁組しましたが、長女の結婚から10年ほど経った頃、被相続人と仲違いしてしまい、それ以来、被相続人ら夫婦と長女夫婦の関係は冷え込んでしまいました。 |
 |
ある日、被相続人が心不全で亡くなりました。相続人は、相談者と長男、二男、長女と養子である長女の夫の5人となります。遺産としては、都内の自宅と、預貯金が約2000万円ありました。遺産のうち自宅は、相談者が被相続人と長年一緒に過ごしてきた場所であり、相談者としては、当然に自分が相続するものだと考えていましたし、長男、二男も同じ考えでした。
ところが、長女は、自宅を自分(長女)が取得する旨の遺産分割協議書案を作成のうえ、「自宅は最終的には母が相続するが、母の財産管理能力に不安があるため、いったん自分の登記名義にして、自分が管理する」と言って回り、相談者らを誤解させて、相続人全員の署名押印を取り付けたうえ、自宅の所有権移転登記を完了させてしまいました。
その後、度重なる要請にも関わらず、いつまで経っても相談者に自宅の登記名義を移転しようとしない長女に不信感を募らせた依頼者らが、当事務所に相談に来られたのが本事案です。
解決方針
 |
依頼者から相談を受けた当初は、依頼者側にとって非常に厳しい事案であるというのが当事務所の率直な印象でした。 というのも、「自宅は長女が取得する」と明記され、相続人全員の署名押印がなされた遺産分割協議書と印鑑証明書が揃っていたからです。 依頼者らにしてみれば誤解であったということなのですが、誤解であった(錯誤による無効)を立証するのが困難であることは明らかでした。 当事務所の方針として、当初は、長女の代理人弁護士に対して、遺産分割の再協議を求めましたが、全く応じる気配がなく、交渉は暗礁に乗り上げそうでした。 |
ところが、長男からこれまでの経緯を改めて聞く中で、長男は、被相続人が亡くなる10年以上も前の頃、妻(相談者)のために遺言書を作成して貸金庫に保管しておいたという趣旨の話をしていたのを思い出し、長女にカマをかける意味で、「貸金庫には父の遺言書があったんだろう?」と聞いたところ、長女からは「あったけど、それが何か?遺産分割協議はもう終わっているけど?」という回答であったという話が飛び出しました。
長女が貸金庫から遺言書を持ち出したはずだと考えた当職らが、長女の代理人に対して、被相続人の遺言書が長女ら夫婦の手元にあるはずだから、こちらに開示するべきこと、また、開示を拒むのであれば、遺言書を破棄・隠匿した者として、相続人の欠格事由にも該当し得ることを伝えたところ、ほどなくして、被相続人の自筆証書遺言原本が当職ら事務所宛てに届いたのでした。
そして、同遺言書には、「被相続人の自宅を含む遺産すべてを妻に相続させる」との内容が書かれていました。
これにより、形勢は一気に逆転しました。
遺言書に基づく所有権移転登記に任意に応じるよう、長女側に対して求めましたが、長女側は任意で応じようとはしませんでした。
そのため、依頼者は、やむなく、長女に対する所有権移転登記抹消登記請求訴訟を提起しました。訴訟においても、長女側は、相続人全員が遺言書の存在を認識していたこと、そのうえで、全員が合意のうえ、遺産分割協議書に署名押印したものであり、協議書は有効であることを主張し、争ってきたため、訴訟は長期化しました。
当事者や長男、二男の尋問が実施され、最終的に、裁判所において、遺産分割協議の際、当事者全員が遺言書の存在を具体的に認識していたとは認められないとしたうえ、依頼者の遺産分割協議に係る意思表示は錯誤により無効であるとして、依頼者側(被相続人の妻)の主張を全面的に認める判決が下されました。
事務所からのコメント
| 解決方針の箇所で述べたとおり、本件では、代理人就任後、相手方ら代理人に対して、遺産分割の再協議をもとめている 状況の最中において、被相続人の遺言書が明るみになるという、異例の経緯を辿った点が特徴でした。 |
 |
これがもし、相手方が知らぬ存ぜぬを通し、遺言書の開示を拒み続けていたとすれば、遺言書を破棄・隠匿した者として、相続人の欠格事由(民法891条5号)に該当する旨を主張していくことになっていたと考えられます。
実際には、相手方側から、当職らの指摘後、速やかに遺言書が開示されました。
本件では遺産分割協議書作成時において、遺言の存在や内容について誰も明確に認識しておらず、相続人間において、遺言内容と異なる遺産分割をすることについて合意が成立していたといえないことは明らかといえました。
その意味で、本件は、後にその存在が明らかになった遺言書が、訴訟の勝敗を左右する決定的証拠であったと言えます。先入観を持たず、依頼者から事実をありのまま聞き出すことの重要性を改めて痛感した事案でした。
<参考判例>
法定相続人全員が自筆証書遺言の存在を知らずに遺産分割協議を成立させたところ、後になって自筆証書遺言の存在が明らかになった場合において、遺言書の相続人の意思決定に与える影響力の大きさ等を考慮し、遺産分割協議の錯誤無効を認めた事例(最判平5・12・16判時1489・114)
大阪の相続・遺言・相続税に強い 入江置田法律事務所の解決事例
※2020年5月28日更新
こんなお悩みありませんか?
相続相談解決事例
相続の争点
この記事の執筆者

入江・置田法律事務所
弁護士・税理士・家族信託専門士
置田浩之(おきた ひろゆき)